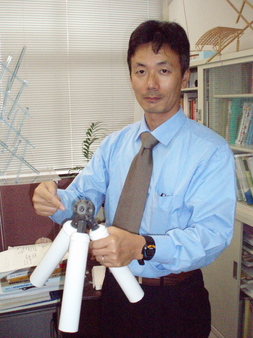神戸市などに多大な被害を与えた兵庫県南部地震は1995年に起きた。当時、現役の新聞記者だった筆者は発生直後から現地入りして取材し惨状を目の当たりにした。この地震をきっかけにして、建築工学研究者の中には理論研究から、より役立つ人命を救う研究に方向転換した方もいる。須田先生はそうした研究者の一人から影響を受けたという。
神戸市などに多大な被害を与えた兵庫県南部地震は1995年に起きた。当時、現役の新聞記者だった筆者は発生直後から現地入りして取材し惨状を目の当たりにした。この地震をきっかけにして、建築工学研究者の中には理論研究から、より役立つ人命を救う研究に方向転換した方もいる。須田先生はそうした研究者の一人から影響を受けたという。
――先生は伊香保温泉で有名な群馬県渋川市の出身ですが、KITに来られた理由は何かあったのですか?
「お恥ずかしい話ですが実は高校時代、あまりに勉強してなくて先生に"君は大学に行くべきではない"とまで言われてしまいました。しかも地元の工業大学だけには行きたくないと思ってました。
そしたら先生が怒ってしまって"お前がそんな贅沢言うな"みたいなことを言われてしまって。"行けるかどうか、受けてみなければわからないだろう"と。それで、あちこち受けて何とか、こちらに受かったというわけです」
――それは、なかなか反骨精神にあふれた高校生でした。博士課程は京都大学に進まれました。何か縁があったのですか?
「KITの修士を出た時は普通に民間に就職するつもりでした。アカデミックな世界に行くつもりはなかったのです。ところがちょうど就職氷河期で採ってもらえなくて。大手の建材・住宅会社の8次試験ぐらいだったと思いますが、重役面接で落とされてしまいました。
夏休みも終わる頃でした。何もやる気がなくなって。そしたら4年生の時にお世話になった京都大学の先生が"じゃ、うちに来るか?" と声をかけてくれて。それで無職というか浪人にならなくて済んだというわけです。積極的に選んだ道ではないのです(笑)」
――建築の構造でも木造系を選んだ理由は?
「あまりよく覚えていないのですが。選んだ研究室が木造系に力を入れていて。いざ調べてみると、いろいろとアカデミックなところが全然解明されていないことがわかりました。これは面白そうだと。
京大の先生がお酒を飲みながら話してくれたのですが、"日本において木造文化がなくなることはないよ。これからも木造をちゃんと研究しないと地震被害もなくならないし、人命を救えない"と。それで"これはやりがいがあるなと思って、そのままのめり込んでいった感じですね」
――なるほど。
「元々その先生が振動の先生で、理論の先生です。だから実験もしないし、ずっと解析ばかりする研究だったのです。論文も建築学会よりも数学の学会などに書かれていました。
その先生が兵庫県南部地震を経験されて、自分の研究があまり役に立っていないことを痛感されたらしいのです。悲惨な状況を目の当たりにして、これは何とかしなくてはいけないと思われて、木造に転向されたのです。そのタイミングでその先生と関わらせていただいたので、今でもずっと一緒に」
外見を保つ耐震化は難しい
――2012年からKITに戻られた。こちらではどんな研究を?
「KITには木造の先生がいらっしゃいますので、私は建築構法とか建築材料をやることになってます。伝統的な木造建築の耐震性をベースに構法的に考えたり材料的に考えたりしています」




 なんとなく建築デザイン系の先生は高校生時代あたりから建築志望一筋といったイメージがあるが、竹内先生は「妥協に妥協を重ねた末」に建築を目指すことになったそうだ。また本気で建築の勉強をしようと思ったきっかけは米国である建築を見た時からだったという。
なんとなく建築デザイン系の先生は高校生時代あたりから建築志望一筋といったイメージがあるが、竹内先生は「妥協に妥協を重ねた末」に建築を目指すことになったそうだ。また本気で建築の勉強をしようと思ったきっかけは米国である建築を見た時からだったという。 山岸先生はKIT教員録の自己紹介欄に「幼少より地震が嫌いであったため、地震に強い建物づくりを目指して建築を志しました」と書かれている。筆者は今まで多くの耐震工学者、建築構造学者に会ってきたが、地震が嫌いだったので耐震を目指したという研究者は初めてだ。
山岸先生はKIT教員録の自己紹介欄に「幼少より地震が嫌いであったため、地震に強い建物づくりを目指して建築を志しました」と書かれている。筆者は今まで多くの耐震工学者、建築構造学者に会ってきたが、地震が嫌いだったので耐震を目指したという研究者は初めてだ。 ----実際に日本でスロッシング・ダンパーが使われた例はあったのですか?
----実際に日本でスロッシング・ダンパーが使われた例はあったのですか?