 山口先生はKITの「教員録」の「横顔」欄に「民間会社の中間管理職で苦しかった時に人生についていろいろ考えました。そのとき、何か人の役に立つことをして“ありがとう”と言われるのが、人生で最も素晴らしいことだと悟りました。大学での教育・研究を通じてそれができれば幸せです」と書かれている。何があったのか?その背景をうかがった。
山口先生はKITの「教員録」の「横顔」欄に「民間会社の中間管理職で苦しかった時に人生についていろいろ考えました。そのとき、何か人の役に立つことをして“ありがとう”と言われるのが、人生で最も素晴らしいことだと悟りました。大学での教育・研究を通じてそれができれば幸せです」と書かれている。何があったのか?その背景をうかがった。
——先生は最初に素粒子物理の研究を志されたそうですが。
「高校の頃から科学系の本を読んでいると、モノは何でできているのかとか、いろいろと基本的なことを知りたくなったのです。究極的には素粒子へ行くのかと漠然と思っていました。さらに関連した本を読んでいると、数式などが出て来てますます面白そうで、すごいなと思ったのです。
湯川秀樹博士のノーベル賞にあこがれたわけではないですが、パイ中間子の話などを読むと、そういう研究をしたいなと思うようになりました」
——それで日本で最難関の東京大学理科一類に入られ、さらに内部でも最難関の物理学科に進まれました。でも素粒子から固体物理に研究の対象を変えられたのは何故ですか?
「素粒子は本当に勉強しようと思うと、数学のめちゃくちゃ難しいものに遭遇するのです。もうイメージできないのです。連続群論とか、そういうものがでてくるのですが、二次元とか三次元とかで頭で想像できるうちはいいのですが、もうちょっと、どうにもこうにも。あれで挫折しましたね。
でも、私のように素粒子研究を目指している人はたくさんいて、ドクターまで行っても助手になれないとう人が続出してくるのです。いわゆるオーバードクター問題というやつです。けれども本当に頭の良い人はドクターまで行かず、マスターで中退して助手として迎え入れられたりするのです」
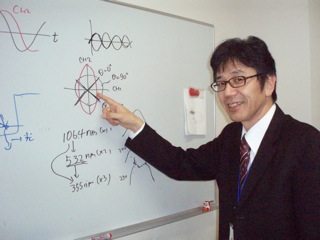 ——やはり固体物理あたりだと少しイメージが湧くから分かり易いですか?
——やはり固体物理あたりだと少しイメージが湧くから分かり易いですか?
「そうですね。固体物理は固体物理でシンプルではありません。素粒子はシンプルにシンプルにといこうとするけれども、固体物理は原子が10の23乗個とか集まっている世界なので、逆にそれをどのように分かり易いイメージにするのかということです。それには絶対に近似を使わないといけないのです。それを理解するのが難しいところだと思いますけれども、何とかなりましたね」
——先生はその後、大学を出られていきなりERATO(えらとー)に入ります。ERATOは科学技術振興機構が実施する大型プロジェクトで、機関・分野を超えた幅広い人材を揃える「人」中心のシステムですね。
「就職活動をしたのですが、行きたいところが見つからなくて。それで東大の工学部にいらした榊(さかき)裕之先生がご自身のERATOプロジェクトに引き取ってくれたのです。ノーベル物理学賞の江崎玲於奈さんの弟子にあたる方です。
“量子波プロジェクト”という名前で、ちょうどそのころ80年代、MBE(Molecular Beam Epitaxy , 分子線エピタキシー法)という結晶成長する層を1原子層ずつ積み重ねて、新たな機能をもつ素材を創ろうという技術が発展していました。電子が波のようにふるまう波動性という量子力学的な現象を利用しようというのです。
固体物理としては最先端の研究だったので楽しかったです。」
——ERATOの後はNECに移られます。
「NEC ではブルーレイのための青色レーザーを開発していました。青のレーザーはまだなかったので面白かったです。ないものを創るというのは。
10年間いましたが、最後の方は管理職になり、研究に手を出せないこともあり、特許の問題もあって結構大変でした。
もう一つ、信頼性という、いかに壊れないように作るかということが、もう泥くさくて泥くさくて。事業部からは“いつできる? いつできる?”と催促される。予算をもらうにも、いろいろなところを工面してたいへんでした。
それで結局、社会に役立つような研究ではだんだんなくなってきたのです。どの企業を蹴落とすかというような、特許でもゲームみたいに相手をひっかけたりなんかして。それで、ちょっとこれは何かおかしいなと思うようになりました。
そうした中で自分の人生を考えて、一つは学術的に真実を追究すること、もう一つは世の中に役に立つことをする、この二つを柱にしようと決めました」
芸術の重要性に目覚めました
——それで転職を決意された。
「ちょうど稲盛財団が学術部を新しくつくるということで、ドクターを持った人を募集していたのです。それで応募したら入れてくれて、すぐに部長にしてくれました。稲盛和夫さんとも気楽に話せるようになりました」
【稲盛財団は京セラの創業者・稲盛和夫氏が設立した財団。1984年より科学や技術、文化において貢献した人に与える国際賞、京都賞を運営している。賞金は5,000万円】
「仕事で一番大きいのは京都賞の準備です。審査をするのは野依良治さんとか大御所の先生方。私は審査をするわけではなくて、資料を整理するだけですが、それが大変なのです。全世界から推薦状が来るので。審査員の先生方の議論を全部要約したりという業務でした。
私の得意な半導体だけでなくて、芸術部門もあって哲学、現代音楽、現代美術もありました。私はそれまで結構、数学至上主義だったので、そういうものに初めて触れました。一応、学術部員は4人、ドクターを持っている人がいて、それぞれの分野を担当するのですが、文系はほとんどいなかったので、“君は音楽好きだから、じゃ音楽やってよ”みたいな感じで。私も美術などを担当したりして(笑)。
知らなかったのですが、芸術は重要な学問だということが、その時、初めて分かりました。稲盛さんの思想にも“科学と芸術は両立しなければならない”というのがあるのです」
 ——先生は06年からKITに来られました。今後はどのような研究を目指しますか?
——先生は06年からKITに来られました。今後はどのような研究を目指しますか?
「光の色は波長の長さによって青から赤までありますね。でも緑の近辺はちょっと波長が違うだけで緑、黄色、橙と目まぐるしく色が変化します。でも、このあたりだけ半導体レーザーがないのです。緑は光の三原色の一つですし、緑色半導体レーザーができればディスプレーなどのありかたがガラッと変わってしまうのです。この開発を目指しています」
京都賞の舞台裏に係ったという先生のユニークな経験が生かされることを期待したい。

