 石原先生は先生自身の言葉を借りると、「かつては製薬会社の技術者だったが、現場で"技術を如何に育て、如何に活かすか"を考え出したのがきっかけで、現在は社会科学的アプローチで企業研究に取り組んでいます」という。その経緯を少し詳しくうかがった。
石原先生は先生自身の言葉を借りると、「かつては製薬会社の技術者だったが、現場で"技術を如何に育て、如何に活かすか"を考え出したのがきっかけで、現在は社会科学的アプローチで企業研究に取り組んでいます」という。その経緯を少し詳しくうかがった。
――先生は東京理科大学のご出身ですが、理科大というと一般にはどちらかというと技術系のイメージが強いですが、先生は応用生物学科に進まれました。何か理由があったのですか?
「大学で何を学びたいかなんて真剣に考える余裕なんかなく、大学受験して受かったところに進んだ、というのが正直なところです。生き物は好きでしたが、高校の生物って暗記ものばかりでどちらかというと苦手意識がありました。
でも、"バイオはこれからブーム"とも聞いていましたし、応用生物と言って、純粋な生物学よりも幅広いし、当時、分子生物学が始まっていましたし、発酵化学もありましたし生物化学とかもありました。高校で唯一関心が持てた化学とも接点がありそうだったので進んでみようかなと思いました。
それと、通学でラッシュに巻き込まれるのは避けたくて、都心の大学には通いたくないという理由から、地方に立地する理科大を選びました。」
――大学院は大阪大学の医学研究科に進まれます。これもユニークです。
「大学で当初は生物が全然分からなかったのですよ。で、自分の専門性を高めたいなと思って、いろいろ勉強していったら、面白いなと思ったのが分子生物学でした。
ある程度分かってきたら、今度は先進的なことに触れてみたいと。純粋なサイエンスではなく、何か社会の役に立つような接点のあるサイエンスをやりたいと医学を志したのです。
学部の担当の先生が相談に乗ってくださって、慶応義塾大学の医学部で研究する機会を与えてくれました。ネズミに"がん"を起こさせるがんウイルスの研究をしました」
――学部でそのようなことが可能なのですね。驚きました。
「それがきっかけで、もっと専門的にやりたいなと思いまして、今度は大阪大学医学部に、医者になるのとは別に医学を学ぶ医科学修士というコースがありまして、そこに入りました。
その後、インターフェロンの研究をなさっている谷口維紹(たにぐち・ただつぐ)先生に師事して最先端の研究をやり出しました。当時はウイルスの防御機能に関わる転写制御因子に着目した研究が盛んで、研究室内の田中先生にご指導いただきながら、その因子の生理機能を追究していきました。
その結果、その因子は生体防御機能に関わるだけでなく、発癌とも関係していることを突き止め、幾つか論文を発表させていただいたりしました。」
*転写制御因子とはDNAの遺伝情報をRNAに転写する過程で、促進したり抑制したりするタンパク質の総称
――その後、民間企業に入られます。
「論文を書くだけでなく、もっと社会の役に立つ仕事がしたいという気持ちを持ち続けていましたので、医薬開発の基盤になるような基礎研究をしたいと思って協和発酵工業に入社して、東京研究所に配属され基礎研究に従事しました。
ところが、数年経って、自分で良かれと思って作った技術を特許にしたのですが、会社の中では評価されず、研究現場から外されてしまいました。自分はどうして失敗したのだろう? これからどうしよう? と悩んでいたところ、私の尊敬する学者である義理の父より「技術をベースにしたマネジメントを色々な視点で学ぶMOT( Management of Technology, 技術経営 )という学問領域ができたから学んでみてはどうか」とアドバイスを受けました。
これまでマネジメントなんて視点を持ったことのなかった私に取って新鮮な話でした。体験授業で内容を確認した上で、職場にも近く、義父にも勧められた理科大のMOT大学院に通いだしました」
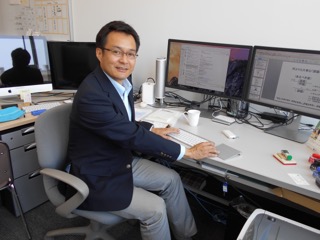 ――ベンチャー企業にもいらしていた。
――ベンチャー企業にもいらしていた。
「自分でも、もう少しチャレンジしたいなと思っていたら、協和発酵の先輩の方が理化学研究所でできた技術を製品開発に活かしたいとビジネスを立ち上げられたので、そこに合流させていただいたのです。具体的には診断薬の開発で、治療現場で迅速に病気を診断するシステム"POCT"の開発に携わりました」
――そして 、とうとうMOTを専門とする研究者になられるわけですね。
「理科大のMOTで私が師事した伊丹敬之(いたみ・ひろゆき)先生から"助教をやらないか"とお誘いを受けて、研究の道に入ることになりました。伊丹先生はもともと一橋大学の先生で、我が国の経営戦略論の第一人者です。
日本企業での技術と経営の関係についても分析してこられた方です。お話を聞くうちに、社会科学でも私がこれまでに培ったサイエンスと通じるものがあると気づいて、社会科学の研究も悪くはないかと」
――KITは技術系大学です。先生のような幅広い視点から技術を捉えて学生の目を開かせてくれる方は貴重な存在です。
「企業と大学、市場と技術、それぞれわかって翻訳ができる人がいないと市場に技術を生かすようなことはできないですよね。僕はそういった技術と市場を結ぶコミュニケーターを育てたいなと思っているのです。
私自身、学生の頃は視野の狭い技術者志望で、こうした視座やその重要性に気づきませんでした。
今は、こうした技術との接し方の多様性と大切さについて、機会があるたびに学生にはお話をしているのですが」
 21美の人気も分析
21美の人気も分析
――先生はKITではどのようなことを教えられているのですか?
「僕は学生に"問題の本質"を見つけ出すことを指導しています。学生が自分の関心のあるテーマについて話してもらい、素朴な"なぜ?"を問いかけて、常識と思われがちな事柄について様々な視点で調べ直して、考え直してもらう。
すると、それまで問題の表面的なものしか見えなかったのが、問題の根本的なものが見えてくることがあるんです。
問題の本質を見つけ出せばゴールは近く、これまでにない効果的な解決策が出やすくなると考えています。だから、私は解決策を考えるのではなく、問題の本質に迫るプロセスをしっかり指導しようと心がけています」
――学生は具体的にはどんな課題をやっているのですか? ユニークな例がありましたら。
「有名な金沢21世紀美術館がありますね。年間150万人が入る、地方としては集客力が飛び抜けて高い美術館ですけども、なぜ、そんなに集客力が高いかという話をすると、創設した市長さんやキュレーターさんたちは"コンセプトが良かったからうまくいったのだ"という話をされて、みんな納得するのです。
でも、それだったら他の美術館も同じようにやっていけば良いのではないの。でも、できているのは21美しかない。なぜ?という疑問を学生にぶつける。学生たちはいろいろインタビューを行い、現場を観察して、観客はどんな人が多いかとチェックして、それを多変量分析という手法を用いて、どの項目が一番強いかと分析している学生もいます」
筆者は数年前に「イノベーションの世紀:アメリカの革新」という米国技術史のビデオ教材シリーズを KIT図書館に寄贈したことがある。石原先生はそれをきちんと見ていて評価してくださった。さらに石原先生とは技術史を学生に教える重要性で一致した。

